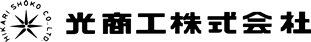技術関連のよくあるご質問
地絡方向継電装置
上記以外のご質問はこちらから
A
(1) 電力会社様DGRとの協調
電力会社様と協議を行い、地絡電流・電圧感度の整定及び時限整定を決定する必要があります。
(2) 受電需要家内での協調
地絡方向継電器は非方向性継電器と異なり、地絡電流感度の整定にあたってはもらい事故を考慮をする必要はありません。 地絡電流・電圧感度の整定については、電路末端から電源側になる程、感度が鈍くなるように各地絡方向継電器の整定タップに差をつけて整定し、時限協調は、それぞれ整定タップに0.3秒以上の差をつけてください。
A
電磁波(電波)ノイズなどの影響を受けることがあるため、配電盤内で2芯シールド線(0.75m㎡ 以上)、またツイストペア線(1.25m㎡以上)を使用し、極力短くなるようにご配慮ください。また、長くなると保守点検の試験が難しくなる点も配慮して、最長でも100m以内でご使用ください。
A
M,N端子に出力される波形は正弦波では無く、下表のような波形となっております。 従ってテスターなどでは測定できませんのでご注意ください。
| 旧仕様品 | 現行仕様品 | 備考 |
| 形式:LVG-2・2S | 形式:LVG-3・3C,LDG-23 LVG-7,LDG-73 LVG-8,LDG-83 |
|
※定常時0V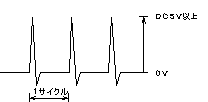 |
※定常時DC11V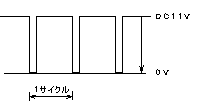 |
動作時に左図のようなパルス信号が出力されます。 |
| LDG-11Dと組み合わせ | LDG-21,LDG-71,LDG-81と組み合わせ |
※ LVG-2・2S及びLDG-11Dは生産中止品です。
※ LVG-3・3C及びLDG-21・23は生産中止品です。
A
(1) 電源側の地絡事故。
(2) 電力会社様の配電線路にV結線の電圧調整器がある場合、三相の対地電圧にアンバランスが生じて見掛け上の地絡電圧が生じてVoランプが点灯する場合があります。
(3) 電路で一相が欠相している場合、または三相電路で単相負荷ケーブルが長い場合に対地のインピーダンスのアンバランスが生じ、見掛け上の地絡電圧が生じて、Voランプが点灯する場合があります。
(4) M,N端子が何等かの原因で短絡、または配線の極性違いがありますとVoランプが点灯します。
(5) 継電器本体の故障によりVoランプが点灯する場合があります。
A
(1) ケーブルシールド層の両端接地
ZCTにケーブルを貫通して使用した時、ZCTのK側及びL側両方でケーブルのシールド層が接地されていると、2点に電位差が生じた場合、ケーブルのシールド層に電流が流れIoランプが点灯する場合があります。
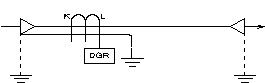
※点線のようにZCTのK側及びL側で両端接地をしていないか?
(2) ZCTの定格電流より大きな負荷電流が流れると残留電流が発生してIoランプが点灯する場合があります。
(3) ZCTの二次配線に電磁誘導や静電誘導などを受けていると、ZCT二次配線間に起電力が生じ、その電圧を継電器が検出してIoランプが点灯する場合があります。
(4) 継電器本体の故障によりIoランプが点灯する可能性があります。
(5) 信号線の多点接地(y2以外の接地)
| 形 式 | ZPC-9 | ZPC-9B |
| 変成器の色 | 黒色 | 茶色 |
| T-E間の動作電圧 (完全接地電圧3Voの5%整定) |
570V | 190V |
※ZPC-9Bは、ZPC-9の3分の1の電圧で試験できます。
A
下記の条件で試験を行ってください。
(1) Vo感度を測定する場合
Ioを整定値の150%印加してVoを除々に上げ、動作したときの電圧値を測定する。
(2) Io感度を測定する場合
Voを整定値の150%印加してIoを除々に上げ、動作したときの電流値を測定する。
(3) 位相角を測定する場合
Ioを整定値の1000%、Voを150%印加して、遅れと進みの動作、不動作の限界位相角を測定する。
(4) 動作時間を測定する場合
Voを整定値の150%印加して、Io整定値の130%及び400%の時の動作時間を測定する。位相角は0°。
※良否の判定基準については、製品カタログの仕様に記入してあります。
A
(1) 電解コンデンサは環境条件により特性経年劣化が生じます。年次点検等では発見できないためオーバーホール等の考慮が必要です。一般的には、7年~10年程度が目安といわれます。
(2) 更新推奨時期は日本電機工業会発行の「汎用高圧機器の更新推奨時期に関する調査報告書」によると、保護継電器の更新推奨時期は15年となっています。
この値は製造者の保証値ではありません。
日常点検及び定期点検の実施を前提とし、新品と交換した方が経済性を含めて有利と考えられる時期となっていますので、更新時期は環境条件などを考慮する必要があります。
A
こちらのページにまとめてありますのでご参照ください。
→【不要動作要因とトラブル事例】
漏電リレー
上記以外のご質問はこちらから
A
高調波対策形とは零相変流器の前後に高調波を発生するインバータ等の機器が設置されていても、不要動作しないようにフィルターを強化してあるものです。
標準製品への高調波対策時期は下表の通り標準化しております。
| 形式 | 実施時期 | 備考 | |
| LEG-120Lシリーズ | 1994 | ||
| LEG-107Lシリーズ | 1995 | LEG-107LN・LF・LA・LAN・LAF LEG-108LN・LF・LA・LAN・LAF |
|
| LEG-108Lシリーズ | 1996 | ||
| LEG-170Lシリーズ | 1995 | LEG-170L・170LF・170L-DC | |
| 1996 | LEG-170LN・170LN-DC | ||
| LSG-5Y・10Y | U-25 | 1994 | U-25 |
| LSG-5W | U-33 | 1996 | |
| U-34 | 1996 | ||
| LSG-6TB・10TB | U-37 | 1996 | |
| LEG-173Lシリーズ | LEG-173L | 1997 | |
| LEG-173L-DC | 1998 | ||
表記実施年の製造品は対策されていないものもあります。製造番号でお問い合わせください。
A
図のように変圧器の並列運転で、それぞれの変圧器の接地線で漏電検出を行うと漏電リレーが動作する可能性があります。
例えば下図のような電路で、負荷電流が20Aであり各トランスから10Aずつ供給した場合、電路の多少のインピーダンスのバラツキによりA変圧器に11A、B変圧器に9A流れたとすると、差し引き1Aの循環電流が接地線を通じてZCTを貫通し、漏電リレーが不要動作します。
このような変圧器の並列運転での不要動作を防止するには、下図(b)のようにZCTを循環電流の流れるループの外側に設置するようにします。
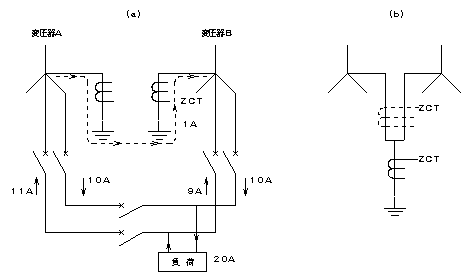
A
並列回路に図(a)のように零相変流器を設置した場合、各相電路インピーダンスのバラツキにより、負荷電流が相殺できなくなり、見掛け上の漏電電流が発生し不要動作する場合があります。例えば下図のような場合、図のように1Aの電流がループ内を循環することになり、この循環電流によって漏電リレーが動作することになります。対策としては(b)のようにループ外または接地線にZCTを設置します。
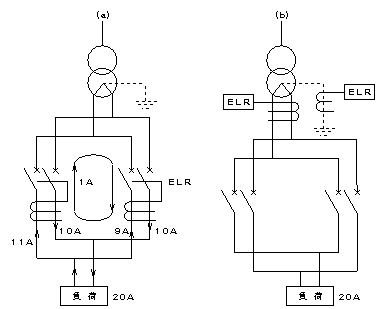
A
図のように接地線を共通にしている電路で、他回路で漏電事故が発生した場合、接地抵抗の電位(VR)が上昇し、健全回路の対地静電容量によりIC1が流れ、漏電リレーが不要動作するものです。
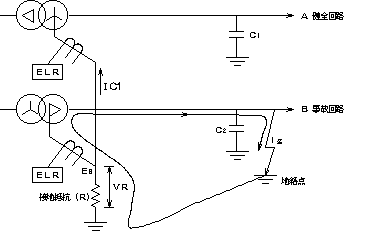
静電容量(C1)としては、配線のもつ静電容量やパソコン等の電子機器のノイズ防止用コンデンサが考えられます。
対策について
(1) 対地静電容量を考慮して、感度設定を鈍くします。
(2) B種接地抵抗(R)を極力小さくします。
(3) 方向性をもったELR(漏電方向リレーLIG-12)を使用します。
アイソレーション システム
上記以外のご質問はこちらから
A
医用室内に分電盤を設置する場合は、医用接地にしてください。分電盤を医用室外、または電気室等に設置する場合でも医用接地が望ましいですが、無い場合はD種接地工事にしてもかまいません。
A
下記リンクにて対処方法を紹介しておりますので確認願います。
https://www.hikari-gr.co.jp/iso_alarm.html
※ 手術中あるいは治療中に動作した場合
手術あるいは治療を中断することはできませんので、充電部に触れないよう十分に注意して警報ブザーを停止し
手術あるいは治療が終了後、医用機器と電気設備(電路の絶縁やコンセントの絶縁)などを調べてください。
| 定格容量 | 全損失(W) | 発熱量(kJ) | 備考 |
| 3kVA | 126 | 454 | 全損失は最大値 |
| 5kVA | 210 | 756 | |
| 7.5kVA | 315 | 1134 |
零相変流器
上記以外のご質問はこちらから
A
当社の零相変流器は、JIS品で規格には規定はありません。
JEC-1201の規格品と異なりますので、200mA:1.5mAのような変流比ではありません。
出力電圧で管理されています。一次零相電流200mAに対して、二次出力電圧17.2mV,100オーム負担となっています。
A
電磁波(電波)ノイズなどの影響を受けることがあるため、配電盤内で2芯シールド線(0.75m㎡ 以上)、またツイストペア線(1.25m㎡以上)を使用し、極力短くなるようにご配慮ください。また、長くなると保守点検の試験が難しくなる点も配慮して、最長でも100m以内でご使用ください。
A
ZCTにケーブルを貫通して使用した時、ZCTのK側及びL側でケーブルのシールド層が2点接地されていますと接地点間の電位差で迷走電流が流れ継電器が不要動作することがありますので、適切な施工をする必要があります。 ケーブルを保護対象とした場合の適切な施設方法の例を図示します。
| 片端接地方式 | 両端接地方式 |
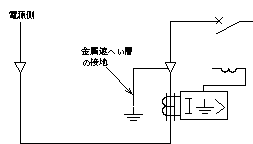 (注) 接地線はZCTを貫通せずに施工する。 |
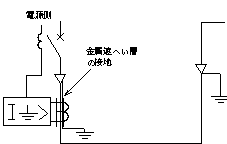 (注) ケーブル電源側の接地線はZCTを貫通して施工する。 |
A
(1) 高圧電路でZCTを使用する場合は、混触対策のためZCT二次側を接地しなければなりません。なお、非方向性と方向性の高圧地絡継電器で、接地方法が次のように異なりますので注意してください。
① 非方向性の高圧地絡継電器を使用する場合は、必ずZCTの l 端子を接地してください。
② 高圧地絡方向継電器を使用する場合は、Z2-Y2端子は継電器内部のプリント基板箔で接続されておりますので、複数あるZCTで各々接地をとると多点接地となり、地絡方向継電器が不要動作する原因になります。そのため、システム上に1つしか存在しない零相蓄電器(ZPC)の二次側端子(Y2)一点で接地してください。
高圧地絡方向継電器の外部接続図例は、こちらをご覧ください。
(2) 低圧電路(600V以下)で使用する場合、零相変流器二次出力端子の接地はしません。